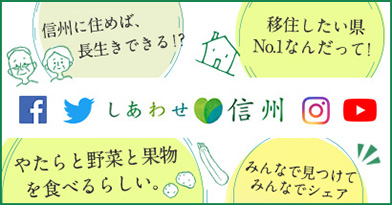ホーム > 県政情報・統計 > 県概要 > 知事の部屋 > 知事会見(動画とテキストでご覧になれます) > 2013年度知事会見録一覧 > 知事会見2013年4月19日
ここから本文です。
更新日:2016年12月26日
知事会見(平成25年(2013年)4月19日(金曜日) 14時00分~15時00分 県庁:会見場)
項目
知事からの説明
取材者からの質問
- 道州制に関する庁内WGの設置について(1)
- 政策会議について
- 三重県知事との会談について
- 発信力向上のための取り組みについて(1)
- 満蒙開拓平和記念館について
- 道州制に関する庁内WGの設置について(2)
- 発信力向上のための取り組みについて(2)
- 発信力向上のための取り組みについて(3)
- 主権回復の日の式典出席について
- 教育委員会改革案について
- TPP交渉に関する今後の県の対応について
- 「山の日」について
- 道州制について
- 道州制に関する庁内WGの設置について(3)
本文
知事からの説明
1 部局長会議を開催、NAGANOものづくりエクセレンス2013、冬の省エネ大作戦2012の取り組み結果について
長野県知事 阿部守一
4月19日(金曜日)の会見を始めます。私からは3点。部局長会議の報告、NAGANOものづくりエクセレンス2013、冬の信州省エネ大作戦・2012の取り組み結果、この3つをお話を申し上げたいと思います。
まず本日の部局長会議ですが、発信力向上のための取り組み、「道州制に関する庁内ワーキンググループ」の設置、平成25年度ふるさとの森づくり県民の集いの開催、職員宿舎に関する基本方針、政策会議の設置、平成24年長野県犯罪の特徴的傾向、少年補導の概況について報告がありました。
このうち、私の方から発信力向上の関連で、統一広報テーマを作って取り組んでいくということについてお話しを申し上げます。かねてから長野県としての発信力を高めようという話をしておりますが、今般、県全体で統一広報テーマを決めて、県職員全体で組織を挙げて、統一的な発信を行っていこうということと致しました。その第一弾として、本日から9月の末まで「しあわせ信州創造プラン」、「信州ハート」の2つをセットで、県全体の統一テーマということで発信をしていきたいと思っています。各職員には知恵を出して、しっかりと発信をしていってもらいたいと思っています。
「しあわせ信州創造プラン」と「信州ハート」、信州ブランド戦略の中での「しあわせ信州」、これは、テーマの中でも大きなテーマだと思っていますので、きっちりと県民の皆さまに伝わるように取り組んでいきたいと思いますし、10月以降もその都度適切なテーマを選んで、各部局それぞれが発信することはもとよりでありますけれども、県組織共通のテーマ設定をして発信していくようにしていきたいと思います。また、今回のこうした取り組みとも合わせて、各部局主管課の課長補佐、地方事務所の副所長を「発信役」として定め、職員の発信力の向上に取り組んでいきたいと思いますし、職員研修もしっかり行っていきたいと思います。
部局長会議の後、株式会社井之上パブリックリレーションズの井之上社長からご講演をただいたわけでありますけれども、改めて県民の皆さまとの協働の重要性・意義を部局長の皆さんにも認識をしてもらえたのではないかと思っております。井之上社長からもお話がありましたが、これからの県政を進めていく上で、まず目標達成、成果にこだわれという話をさせていただいてますけれども、「目標・目的を達成する倫理観に支えられた『双方向性コミュニケーション』と『自己修正』をベースとしたリレーションズ(関係構築)活動」は協働を進めていく上で大変重要な概念だなと思っておりますので、こうした点も含めて県の職員が共有できるようにしていきたいと思います。1点目は、統一広報テーマを決めて発信力をさらに向上していきたいというお話しでございます。
それから、部局長会議に関連してもう一つは道州制の関係であります。道州制に関する庁内ワーキンググループを設置するということに致しました。国においては道州制基本法案を提出するという動きも出てきているやに聞いておりますけれども、この道州制の問題は日本の形をどうするか、地方自治というものをどう位置付けるかという観点で極めて大きなテーマだと思っています。
私自身は道州制について慎重な立場でありますし、市長会総会のあいさつでも申し上げてきましたけれども、関西経済界の皆さんとお話をしたときにも、経済界の皆さんの感覚は共有するけれども、日本が直面している課題に対応する唯一最善の答えが道州制だとは私は思っていないと話をさせていただきましたけれども、少し県庁の組織として、この問題を掘り下げて考えていきたいと思っています。そういう観点でワーキンググループを設置して、県としての考え方を明らかにしていきたいと思っています。併せて長野県における地方自治の在り方、自治の仕組みをどうするかということも考えていく必要があると思っています。ワーキンググループの検討状況等については皆さまにも報告していきます。
大きな2点目でありますけれども、プレスリリースの資料にございます通り、長野県として誇る優れた技術・製品の認定制度「NAGANOものづくりエクセレンス2013」ということでスタートさせていきたいと思います。ものづくり産業は長野県の「稼ぎ頭」と考えておりますし、「しあわせ信州創造プラン」の中でも次世代産業の創出ということを位置付けて、県内企業の優れた技術、さらに磨きをかけていただくように県としても側面からサポートしていかなければいけないと思っております。そうした中で、県内企業の革新的・独創的な技術あるいは製品を、県として「NAGANOものづくりエクセレンス」ということで認定をして、国内外に広く周知をしていきたいと、また併せてそうした技術・製品を有する企業に対しての支援というものも行って、事業展開を促進していきたいと考えています。選考プロセスは、ものづくりNAGANO応援懇話会、経済界のトップ等で構成される場がありますので、そこの場を活用させていただいて、県として県内企業の優れた技術・製品を認定していく形にしていきたいと思っております。素晴らしい技術・製品につきましては、信越放送などのご協力もいただきながら、国内外に発信をしていきたいと思っておりますし、認定技術・製品を有する企業に対しては、ものづくり産業応援助成金での優遇であるとか、あるいは海外展示会への出展の優先取扱い等の支援策を新たに設けて、さらなる技術開発を促していきたいと考えています。また、このものづくりエクセレンスに加えて、産業政策課のホームページに全国規模で表彰を受けた企業であるとか、あるいは海外トップシェアを占める製品といった県内企業の魅力を発信するページ「ながのエクセレントカンパニー」というものを新しく設けて、長野県産品の価値の向上・発信に努めていきたいと考えています。なかなかこれも長野県として発信の一環でありますけれども、良いものをいっぱい持っているけど、なかなか伝えきれてないと思っておりますので、こうしたことも含めて今回この部分は長野県の製造業の強さ・素晴らしさというものをしっかり発信していきたいと考えています。
それから最後3点目でありますが、県民の皆さま方へのお礼とご報告ということで、冬の信州省エネ大作戦2012の取り組み結果についてでございます。結論から申し上げると今回目標マイナス3パーセント、平成22年度比マイナス3パーセントという目標でありましたけれども、それを大きく上回る7.2パーセントの節電、ピークカットということで、県民の皆さま方のご協力の中で成果を上げることができたと思っております。この場をお借りして、ご協力いただいた全ての皆さんに御礼を申し上げたいと思っております。また、県の機関でも22年度比5パーセント削減ということで目標を掲げ取り組んできましたけれども、県庁舎においてはマイナス8.6パーセント、合同庁舎ではマイナス12.9パーセントということで、いずれも目標を上回ることができました。この省エネルギー、省電力ということは、新しい総合5か年計画である「しあわせ信州創造プラン」の中でも、「環境・エネルギー自立地域の創造」ということをうたっているわけでありまして、外部要因にかかわらず長野県としてしっかり取り組むべき課題だと考えています。そうした観点で、ぜひこれからも省電力、節電・省エネルギー、県としてしっかりと取り組んでいきたいと思っています。今回、信州あったかシェアスポット、あるいは信州省エネパートナーということで大勢の皆さまにご協力いただいたわけでありますので、今後とも県民の皆さま方との協働の中でさらなる省エネルギー・省電力を進めて、新しいライフスタイル、あるいはビジネススタイルの定着を進めていきたいと考えているところであります。夏に向けて、夏の対策ということも考えていかなければいけないわけでありますけれども、今国において検討行われておりますけれども、ぜひ長野県としては引き続き数値目標を掲げる中で、しっかりとした取り組みを県民の皆さんと行っていきたいと考えています。私の方からは以上でございます、よろしくお願いします。
取材者からの質問
1 道州制に関する庁内WG(ワーキンググループ)の設置について(1)
信濃毎日新聞 牛山健一 氏
道州制に関する庁内ワーキンググループについてなんですが、2月県会の知事の表明の内容ですと経済界や市町村も交え検討する場を考えていきたいというおっしゃり方だったと思います。今回は庁内のこの研究組織ということで、市長会、町村会とも連携してっていうふうには目的には入っているんですけれども、市町村との道州制のですね問題の検討していく場というのは、例えば別に設けるのか、そこら辺共有の仕方というのどういうふうに考えていらっしゃるのか教えてください。
長野県知事 阿部守一
道州制の問題は、行政だけ県だけの問題ではないと思っておりますので、県庁の中だけで粛々とやればいい話だとは思ってないです。ただ、とはいえ県庁の中でしっかりとした考え方を持たずに進めていくわけにもいかないわけでありますから、ワーキンググループをまず作って、県としての基本的な考え方、論点、そういうものを出した上で市町村をはじめ関係する皆さま方とどういう形で進めていくのがいいのかということはまた相談をさせていただくようにしたいと思います。
2 政策会議について
信濃毎日新聞 牛山健一 氏
それからすみません、政策会議なんですが試行もされていたということなんですが、私の持った印象で恐縮なんですけれども、政策会議はある意味事前にしっかり調整するということも重要だとは思うんですが、ややもすると、今日行われた部局長会議が形骸化することにならないかなと印象を持ったんですが、その点どうでしょうか。
長野県知事 阿部守一
全くそういう感覚は、私はないですね。むしろ、部局長会議での議論を私はもっと活性化させなければいけないと思っていますので、それはそれで、しっかりと部局長会議で各部局長がより積極的に部局の殻を破ってですね、発言してもらいたいと思いますし、またそういう環境を私もつくっていかなければいけないだろうと思っています。むしろ政策会議は、私はより踏み込んで政策課題をですね、しっかりと各部局がまず共有して、方向性について考えていく習慣を付けていかなければいけないと。皆さん部局長会議をご覧になられてどういう感想をお持ちになっているか分かりませんけれども、あそこの場で政策がみるみる議論されて出来上がっているという感覚はどなたも多分お持ちになっていないんじゃないかと思います。そういう形式的な形に私はこだわるのではなくですね、むしろ部局長が実質的な議論をしていくということが、これは県民にとって必要だと判断しておりますので、そういう観点で政策会議を通じてですね、それぞれが持っている課題をより共有をしていってもらう、そして問題意識を共通にして、県政を進めていく、そういう体制を作っていきたいと思っています。
3 三重県知事との会談について
信濃毎日新聞 牛山健一 氏
もう1点、すみません。三重県知事との会談ですが、三重県といえば「子育て同盟」、その前に「ふるさと知事ネット(ワーク)」ですか、連携というか一緒にやられている知事でありますけれども、なかなか同じ中部県知事会で一緒とはいえ、こうしたつながりもあるとはいえ、なかなか遠いところではあるんですが、そこら辺、この会談の狙いについて今一度教えてください。
長野県知事 阿部守一
これは三重県知事の方から投げ掛けで今回こういう形で行うということになったわけですけれども、私は、いろんな地域との連携・補完ということがこれからの地域経営では大事だと思っています。都市部、大都会との補完・連携ということも必要だと思いますが、例えば三重県と私ども長野県、共通する部分と全く違う部分と両方あって、例えば先般の2月議会の提案説明で御杣山(みそまやま)、木曽から式年遷宮の木材を搬出しているということでは、三重県とつながりがあるわけでありまして、実はもっともっとそういうところは共通のテーマとして発信をしていく可能性があるんじゃないかと思いますし、例えば農水産物をみれば、私ども長野県は海がないところでありますけれども、三重県は海の幸が豊富なところであります。逆に、三重県は長野県、例えば長野県ほどワインの特産地ではないということもあるので、そういう部分も一緒になって取り組むことが考えられないかと問題意識もあります。いずれにしても、これから地域の発展を考えていく上では、狭い、閉じた発想では何も物事が進んでいかないと思っておりますので、他の都道府県との協力・連携、こうしたものも基本に据えて取り組んでいきたいと思っています。
4 発信力向上のための取り組みについて(1)
朝日新聞 軽部理人 氏
発信力の向上のことについてお尋ねしたいんですが、知事としては今現在、発信力が長野県はあるとお思いですが、ないとお思いですか。
長野県知事 阿部守一
あるかなしかの○と×の二者択一ではないと思いますけども、本来伝わっていてもいいものが伝え切れてないのではないかという問題意識はありますね。まだまだ長野県の良さ、強さ、そうしたものを発信していく余地は相当程度あると思っていますので、そういう意味で、なんというか十分発信し切れている状況ではない、そこを改善していこうと思っています。
朝日新聞 軽部理人 氏
具体的に知事自らが何かエピソードで、もうちょっと強めなきゃいけないなという危機感感じたことは今までにありますか。
長野県知事 阿部守一
いつもいろいろ感じますけれども。よくいろんなところで例示で言わせていただいていることは、例えば自然エネルギーの取り組みを各県知事と並んで私が発表させていただいたときに、これは私の取り組みも十分でないという反省点でありますけれども、作ってもらったパワーポイントは「長野県の取り組み」、これは長野県としてはすごく真面目なスタンスなんですよ。それ自体は良いことな部分も、もちろんあるかもしれませんけれども、他の県は地元の企業がやっていることとか、市町村がやっていること、それはもう長野県じゃなくて、○○県としてはこんなことをやられていますよということを発信しているわけで、そういう意味の、なんていうか謙虚さというかですね、妙な真面目さというところが、実は発信をするに際しては、足かせになっている部分もあるんじゃないかと思いますし、常々協働ということを繰り返し言っていますけれども、やっぱり今みたいな発想も他の県内の他の主体がどんなことをやっていることに対して常にアンテナを高く張っていなければ、自慢もできないということで、そういう意味でこれは一朝一夕に全てが変わるというわけではないわけですけれども、協働とか発信とかですね、皆さんもここで聞いていると耳がタコになるほど私から聞かされていると思いますけれども、まだまだ県の職員全体に伝わり切れていない部分もあると思いますし、まだ変わり切れていない部分もあると思いますので。当面というかですね。かなりの期間、私は言い続けていかなければいけないなと思っていますし、ぜひ、県の組織全体が、そういう方向に変化をしていってもらいたいと思っています。
朝日新聞 軽部理人 氏
今日、研修会で県民との双方向性というのでしょうか。というようなお話もあったかと思うのですが、例えば、東京都の猪瀬知事なんかは、全部局にツイッターアカウントを開設させたりですね、佐賀県の武雄市は、全職員にツイッターのアカウントを開設させたりとありますが、そういったようなお考えは特にないでしょうか。また、阿部知事のツイッターアカウントが、最近更新されていないようですが、どういった時に更新されているか教えてください。
長野県知事 阿部守一
そうですね。県でも、例えばツイッターとか、フェイスブック等を活用している事例もあるわけで、これは、各部局同じでやれというよりは、むしろ各部局が主体的に考えてほしいと。これだけ発信だとか協働だとか言っているわけですから。そういう手とり足とり画一的にやる必要は、私はないのかなと。部局によって発信の仕方とか、発信の必要性というものは、必ずしも一緒じゃないわけでありますので、そこは県の職員もこの会見を聞いているわけですから、そこは考えてもらいたいと思います。それから、私自身の発信ですけれど、ツイッターとフェイスブックと実は両方やっていて、確かにツイッターの発信量は、最近少ないと思っています。私の感覚からするとツイッターは、実はすごく情報量が少ない、文字数が限られているという所があって、最近はフェイスブックの方が中心になっているというのが、私の今の率直な感覚であります。双方向性という観点からも、フェイスブックの方が、一覧で、双方向というか、私のコメントに対する反応が、ストレートに見れるということがあるので、そうした観点でフェイスブックの方が中心になってきていると思います。ただ、まったくツイッターを止めてしまっているわけではないのでですね。随時ツイッターでのつぶやきというのも行いたいと思いますが、文字通り、ツイッターの方は、つぶやきでありますから、県としての考え方とか、私としての考え方、なかなかいつもツイッターをやっていて感じているのは、自分の書きたいことを書くと、全部字数が足りなくなるので、どこの文字を削ろうかとか、どの点を削ろうかというので結構時間がかかってしまうものですから、そういう意味ではフェイスブック中心になっているというのが今の現状です。
朝日新聞 軽部理人 氏
はい、ありがとうございます。
5 満蒙開拓平和記念館について
毎日新聞 仲村隆 氏
4月25日に南信の阿智村に、満蒙開拓平和記念館が開館しますけれども、この開館に関しては、県の方もいろんな支援をされているかと思うのですけれども、それについてご所見を伺いたいのですが。
長野県知事 阿部守一
はい。満蒙開拓平和記念館については、本当に関係者の長年の思い、念願が、やっと具体的な形になるということで、私としても大変うれしく思っておりますし、開館が間近に迫っているということに対して、大きく期待しているところでございます。満蒙開拓は、国策として進められて、全国から27万人もの開拓団員が送られて、長野県からも約3万3千人の方々が、入植されたわけですけれども、敗戦の混乱の中で約半数もの方々が、祖国に帰ることができなかったという大変つらい歴史があるわけであります。われわれが、今非常に平和な社会で暮らしているわけでありますけれども、こうした過去の歴史の中で、今日のわれわれの暮らしがあるということを、しっかりと、常に思い起こさなければいけないと思います。そういう意味で、この満蒙開拓の歴史というものを、次の世代に引き継いでいく拠点ということが、今回の満蒙開拓平和記念館の意義だと思っております。県としても、建設費の助成を行わせていただきましたし、県立歴史館におきましては、昨年満蒙開拓の歴史を振り返る企画展を実施をさせていただきました。また、この度の記念館の企画展示にも協力させていただいているところであります。ぜひ、関係者の皆さま方の力で、この満蒙開拓の歴史を風化させないように、しっかりと引き継いでいただきたいと思いますし、そのための拠点として満蒙開拓平和記念館が、十分その機能を発揮していただくことを心から期待したいと思っています。
毎日新聞 仲村隆 氏
この記念館の建設に関しては、8年ほど地元の日中友好協会の関係者の方たちが、いろいろな形で努力をされてきて、それでやっと開館にたどり着いたという状態ですけれども、その過程の中で、要は建設費のお話で、なかなかできなかったという経緯があるんですが、それに関して、特に知事の決断というか、お考えで補助の方を予算化したことが、かなり、今回の実現につながったという大きな部分になるかなと思うのですけれども。
長野県知事 阿部守一
はい。私の思いを申し上げれば、満蒙開拓の問題というのは、先ほど申し上げましたように、これは長野県の問題だけでないわけでありますので、本来はこうした施設に対して、国がよりですね、積極的な関心を持って対応していただきたいと思っています。ただ、これは国に言っても正直たらい回しというかね、どこが、どこの省庁が担当するかはっきり分からないと。こっちに言ってもあっちだということの繰り返しであったということは、これ事実なわけでありますけれども、そういうことをいたずらに繰り返していては、関係の皆さま方もどんどんご高齢になられていく中で、先ほども申し上げたように、満蒙開拓の歴史を引き継いでいくことが難しくなってしまうと私は考えましたので、そういう意味で、県として助成をさせていただく中で、建設をしていただくということにさせていただいたわけであります。もっと言うとこれ、県だけではなく地元の市町村、広域連合、そうした皆さんの協力の中でできているわけでありますので、ぜひですね、本来こういうものは国が関心を持つべきですけれども、そういう対応がなかなか十分なされない中で、地元の皆さん、市町村の皆さんと一緒になって取り組みを進めようということで、今回の記念館の開館につながったと考えています。
毎日新聞 仲村隆 氏
分かりました。ちょっとお話がずれるのかもしれませんけれども、満蒙開拓については、かつて行かれた団員の方たちが、結局国策でわれわれは行ったと。ところが、国なり行政は、行くときには行ってくれというかなり熱心な勧めはあったけれども、帰ってくるときにはかなり冷淡であったと。要は、自分たちは棄民であると。そういうことをおっしゃる方たちがかなりいらっしゃって、国や県の責任についてもおっしゃる方もいまだにいらっしゃると思うんですけれども、そういった中で、例えば長野県ですと、かつての西沢権一郎知事なんかは、かつて拓務課長、つまり県の満州開拓の担当者として、たくさんの、3万3千人の方を送り出していくという役割を果たしたという、そういう重い歴史があったりするかと思うんですけれども、そういった中での県自身の責任については、知事自身どういうふうにお感じになっていらっしゃるでしょうか。
長野県知事 阿部守一
これは、過去の歴史をやっぱり行政としても直視をしていかなければいけないだろうと思います。そういう意味で、こういう記念館に支援するということも過去の歴史を直視してですね、そうした悲惨な出来事が二度と繰り返されないようにするためという思いも込めさせていただいておるわけでありますけれども、私が知事としての思いとか考え方、そうしたものについては、これは平和記念館の開館の際もお伺いをさせていただこうと思っておりますので、そうしたときにですね、しっかりと関係の皆さま方にお伝えをしていきたいと思います。
6 道州制に関する庁内WG(ワーキンググループ)の設置について(2)
市民タイムス 渕上健太 氏
道州制のワーキンググループと統一広報テーマの関係で、ちょっと補足でそれぞれお聞きしたいんですけれども、道州制のワーキングの方は国への提言を行うということが書いてあるんですけれども、スケジュール的なものがまずあれば教えていただきたいんですが。
長野県知事 阿部守一
早くやるべきものは早くやらないと、国の議論はかなり速く進みかねないですね。国会の中でもおそらく必ずしも一つの考え方でまとまっている状況ではないのではないかとお伺いをしていますけれども、できるだけまず基本法に対する考え方っていうのは、早急に法案が提出されるというようなことになればですね、取りまとめていかなければいけないだろうと思っています。また、先ほども言いましたけれども、道州制の話は、何度か道州制という制度に対して意見を言っているというだけではいけない話でありまして、足元の自分たちの自治の在り方をどうするかということも並行して考えていかなければいけないわけでありますので、そういう部分については、何というか拙速に走るのではなくてですね、少し論点が整理された段階で、市町村の皆さまとも問題意識を共有して、どういう形で進めていけばいいのかということは考えていかなければいけないだろうと思いますので、道州制に関する庁内ワーキンググループということになっていますけれども、何というか単一的に一つの問題をいつまでにこれやって、次これというような単純な話にはならないだろうと思います。
市民タイムス 渕上健太 氏
進め方というかですね、第一回目が大森先生を呼んで、そのあと意見交換ということになっていますが、今後第二回目以降のざっくりとしたワーキンググループの進め方的なところで少し考えがあればお聞かせいただきたいんですが。
長野県知事 阿部守一
これは、私としては、まず基本的な部分とそれから各論の部分と両方あると思います。第一回目は大森参与にもご参加いただいて、全体的な問題意識の共有をしていきたいと思っておりますが、その上で道州制、これ今構想されている道州制の形が必ずしも判然としてないんで、なかなかそれに対して具体的な考えを整理するのも難しい部分もありますが、ただ、今まで議論されてきているような道州制が仮に実現されたときに、それぞれの政策面、各部局が受け持っている分野でどういうメリット・デメリットがあるのかとかですね、どういう課題があるのかっていうのは整理をしていきたいと思います。そういうものを持ち寄っていただいた上で、県としての道州制についての基本的な考え方というものを整理していきたいと思います。
7 発信力向上のための取り組みについて(2)
市民タイムス 渕上健太 氏
あと、統一広報テーマの関係ですが、私の理解が浅くてあれなんですが、4月から9月が「しあわせ信州創造プラン」ということになっているんですが、それと、またこの10月から3月までがまた新しいテーマを掲げてという・・・。
長野県知事 阿部守一
そうです。最初のテーマが「しあわせ信州創造プラン」と「しあわせ信州」なんで、これ、どっちかというと、あえて統一広報テーマにしなくても県庁全体でやらなければいけないテーマみたいな話があるんで、少しそこの混乱が、誤解されるところがあるかもしれませんけれども、まず最初のテーマとしては、当面の最優先課題である「しあわせ信州創造プラン」、それから「しあわせ信州」、ブランド戦略の「しあわせ信州」を、これ発信していこうと、広報していこうというものでありまして、そのあと10月以降もちろん、「しあわせ信州創造プラン」自体なくなるわけではありませんので、そういうことも伝えてきますが、重点的になっていくものとしては、また別のテーマを決めて取り組んでいこうというものであります。
市民タイムス 渕上健太 氏
今後も年、上期と下期というような形でテーマを分けて発信していくという・・・。
長野県知事 阿部守一
今回、4月から9月となっていますけれども、テーマによって夏だけだとか冬だけだとか、あるいは半年とか3カ月とかじゃなくて1カ月だとかですね、それはテーマによって、必ずしも画一的には考えないで対応したいと思っています。
市民タイムス 渕上健太 氏
2番のところで、各地方事務所ごとに広報計画を作成するとあるんですけれども、これは、今はそういった広報計画というものがあるところもあるし、ないところもあるというような形で、今回この後はすべて作ってもらうという・・・。
長野県知事 阿部守一
これは、例えば各部それぞれ広報計画を持って、例えば「おいしい信州ふーど(風土)」だったらいつこんなことやりますというのは当然作っていますし、県全体であれば広報県民課がもちろん持っているわけですけれども、ここに書いてあるのは今回の統一テーマについてこういうことをやる、新しくやっていこうと、そういうものであります。今までももちろん何にもないわけではないですけれども、統一テーマを作ってやっていくときに、各部局、地方事務所もそういうテーマに則したプランを作ってくださいと、そういうことです。
8 発信力向上のための取り組みについて(3)
信越放送(SBC) 熊崎陽太 氏
統一広報テーマについてお聞きしたいんですけれども、ちょっと基本的な質問になってしまうかもしれませんが、「しあわせ信州創造プラン」ですね、これまでは長野県総合5か年計画という言葉が先行して出ていたんですが、はやりこの「しあわせ信州創造プラン」というこの名称ですね、県民への親しみやすさ、知事の中でどういった点を意図されているのかといった点をお願いします。
長野県知事 阿部守一
長野県、今まで総合5か年計画という呼称でずっと使ってきています。そういう意味で今回も、本来、私はずっと新しい総合5か年計画ということで、県民の皆さんにもお伝えしてきたわけですけれども、率直に言って、自分で県民の皆さんにお話ししながらですね、堅いなと、非常に。堅いし、今は新しいって付けていますけれども、そのうち新しくなくなったら総合5か年計画で、全然個性がないわけですよね、5か年計画の、個性がないというか現れないというか伝わらないわけでありまして、今回の計画自体はブランド戦略と並行して策定をさせていただいて、ブランドの方は「しあわせ信州」、そしてこちらの計画の方は「しあわせ信州創造プラン」ということで、併せて県民の皆さんに深く浸透していってもらいたいなと。そして、やはり、総合5か年計画って何か堅いイメージですけれども、私はこの計画自体県民の皆さんと目標を共有して、県民の皆さんと一緒に実現する計画だっていうのを常々言ってきていますので、そういう意味で県民の皆さんに親しみやすい名称、そして県民の皆さんにもぜひ呼んでいただきたい愛称として、「しあわせ信州創造プラン」ということで付けさせていただいていますので、ぜひこの名称をですね、広げていただきたいなと思っています。
信越放送(SBC) 熊崎陽太 氏
3月末に実施した県民の世論調査で県民の半数近くが内容は知らないというような結果が出たわけなんですけれども、今回の、この親しみやすさを重視したといえるこの「しあわせ信州創造プラン」、冊子も作ったということで、今後、例えば知事が直接県民と接する中で、これを周知といいますか、ともに共有するような時間というのは持とうというような予定は。
長野県知事 阿部守一
それは、どんどん。今の予定は、広報県民課長の方から。
総務部広報県民課長 土屋智則
知事が直接県民と接する中でということにつきましては、県政タウンミーティングを予定しております。先にプレスリリースもしてございますが、5月から6月、7月にかけて東北中南信で各1回、4回をこの「しあわせ信州創造プラン」をテーマとしたタウンミーティングということで計画をしてございます。
長野県知事 阿部守一
あと、私のコメントも入れたビデオメッセージみたいなものも作ってですね、広く普及をさせていきたいなと思っています。これまでの総合計画より相当踏み込んで県民の皆さんにお伝えをしていかなければいけないと思っていますので、ぜひそこは工夫をさらにしていきたいと思いますし、また、県民に伝える良い手段があればまた教えてもらえればありがたいと思います。
9 主権回復の日の式典出席について
長野放送(NBS) 中村大輔 氏
28日に政府が行う主権回復の日の式典がございますけれども、知事出席を決めたようでして、ご承知の通り沖縄の方であまり快く思ってらっしゃらない方も少なからずいる中で、今回ご出席する理由をお聞かせください。
長野県知事 阿部守一
今回の主権回復の日の式典、沖縄の中でもさまざまなご意見があるとは私も報道等で承知をしている中で、慎重に対応を考えました。沖縄県、私が今伺っている状況では沖縄県が不参加ということだとまたこれは非常に沖縄県が違う扱いという形になるのは、私は好ましくないと思いますけれども、沖縄県は副知事が参加されると伺っておりますし、政府主催という形で陛下もご出席されるということで伺っておりますので、そういう意味で私としては長野県を代表する立場としてこれは参加をすることが望ましいだろうということで参加、出席させていただくことにしています。
長野放送(NBS) 中村大輔 氏
知事としてはどんなお気持ちで出席しようと思ってらっしゃいますでしょうか。
長野県知事 阿部守一
これは、日本の今の社会というのは、先ほどの満蒙開拓の話ではないですけれども、かつての悲惨な戦争の歴史の上に私は成り立っていると思います。そういう意味でサンフランシスコ講和条約が発効して、その時点でも今の日本の領土すべて完全に主権が回復されたわけではないわけでありますけれども、そうした沖縄の皆さんの思いも含めてですね、歴史をしっかり振り返って認識して、そして未来志向でこれからの日本という国の在り方を考える日ということにしていかなければいけないだろうと私は思っています。
10 教育委員会改革案について
毎日新聞 小田中大 氏
15日なんですけれども、政府の教育再生実行会議の方で教育委員会制度について改革の提言が出されましたが、今回教育長の権限を強化するということと、教育委員会委員の方の役についても見直すべきではないかということで、詳しくは中教審(中央教育審議会)の方で今後審議される予定ですが、提言案について知事がご覧になられた範囲でのご感想を伺えればありがたいんですが。
長野県知事 阿部守一
私は常々教育行政についての責任の所在が不明確ではないかということを申し上げてきているので、責任権限の明確化を指向するということにおいては、そういう観点でご議論されているのかなと思います。ただ、今もお話があったように、詳細な設計が中教審での審議に委ねられているという形になっているわけで、例えば私からすれば教育行政における知事と教育長との責任なり権限の在り方の具体的な分担というものをどういう形にしようとしているのか、今の状況ではなかなかまだはっきりとしていない部分があるんじゃないかと思いますし、加えて、国の関与が強まるような方向付けがされているわけで、これは分権の観点からももとよりでありますけれども、私は常々「開かれた学校」とかですね、学校現場に近い人たちが学校の在り方を考えられる方が望ましいんじゃないかと申し上げているわけで、その点については少し方向性が私の想いとは逆な部分もあるのかなと。むしろ現場に近いところに、例えば義務教育であればもっと市町村にですね、あるいは地域の皆さんが参加できる場にですね、権限を持ってもらう、責任を持ってもらうということが望ましいと思いますが、今回は国が何ていうんですか、是正勧告、是正命令、何か直接関与するようなことが記載をされているわけですけれども、現実問題そういうことが本当に可能なのかどうかということも含めて考えると、少しその点においては、少しというかかなりですね疑問とする部分もあります。
毎日新聞 小田中大 氏
なるべく地域に近いところでいう面でいきますと、いわゆる県費負担教員の人事権については市町村に検討の上で移譲することも良いのではないかという旨があるので、その点はおそらく評価される部分になってくるかと思うのですけれども、実際国が確かに是正とかですね勧告をしていくという一文が入っていることで、なかなか評価としては難しいとは思うのですが、国としては逆にどのような在り方で教育行政、地方の教育行政に関わるべきであろうとお考えでいらっしゃいますか。
長野県知事 阿部守一
個別具体的なことは関わる必要はないだろうと私は思いますね。何ていうか基本的な教育の在り方とか、今でも学習指導要領で、学習内容については全国基本的に統一されているわけでありますから、何ていうか実際の学校経営なりマネジメントのところは、これは公立学校であれば地方公共団体、私立学校であればそれぞれの学校法人等に委ねていただくということで、個別具体の事象に対して国が直接指揮命令する、あるいは関与するということは、私は必要性がないのではないかと思います。むしろ、これはちょっと教育委員会の政治的中立性という議論もよく議論の俎上(そじょう)に載るわけでありますけれども、これは国の場合は文部科学大臣が内閣の一員でもあるわけでありますので、国が直接指揮監督に近いような形で関与するというのは、教育の中立性というような観点ともベクトルが違うのかなと私は思います。
11 TPP交渉に関する今後の県の対応について
信濃毎日新聞 古志野拓史 氏
TPPに関連してなんですけれども、今政府の試算が3月にあって、それだけだと地方はなかなか農産物なんかへの影響を直接的には試算できないというような仕組みになっているそうで、県の国への照会に対する回答でもそういう内容になっていたようなんですが、県としては何らかの形で農業分野なんかを中心に試算をしていかれるというようなことでよろしいですか。
長野県知事 阿部守一
これは、国のやっているような形の試算は、なかなか県境の、県域内での影響額だけっていうのは、しっかり出しづらい、計算上出しづらいところがあるわけですけれども、一定の試算というものはしていく必要があるだろうと思います。
信濃毎日新聞 古志野拓史 氏
それで知事は、3月の庁内の対策会議の際にもですね、経済的な観点だけで論じられているのはいかがなものかというようなお考えを述べられていますけど、その辺も踏まえて県としての試算にどんな視点が大事になっていくかという思いと、かなりその後の交渉参加に向けた手続きというのは加速化しているようなんですけど、その辺の現状についても今お考えがあれば伺いたいのですが。
長野県知事 阿部守一
まず今お話があったように、経済的な側面だけで測れない、例えば農業の多面的な価値みたいな話は、農業生産額が一億円落ちましたと、だから一億円他の分野で取り戻せばこれでプラスマイナスゼロですというのは、私はちょっと違うだろうなと思っていますので、そういう意味で影響額の試算ということ自体が、それだけで一人歩きしてすごく意味があるとは私自身はあんまり考えていないです。むしろ、この経済的なグローバル化の中で、もちろん国際社会がどう共同分担するのが最適なのかということは考えなければいけないと思いますけれども、私の価値観はむしろ企業利益だとか、利益が極大化することが価値ではなくて、それぞれの国々の人々の暮らしが一番幸せが感じられる形になるのが最適だと思っていますから、そういう観点で考えると単に数字上こっちがこれだけ得してこっちがこれだけ損しているということとは違った角度からも考えなければいけないのではないかなと思っています。そういう意味で、ぜひこれは国民的議論の中で最終的な決断をしてもらいたいと思っていますけれども、経済的なプラスマイナスという価値観だけではない価値観をぜひ視野に入れて、国においては考えてもらいたいなと思います。
信濃毎日新聞 古志野拓史 氏
それで試算なりを出すにあたっては、時期的にはそんなに悠長にも構えてはいられないような状況かなと思うんですけれども。
長野県知事 阿部守一
それはそんなに時間かからずに出せるよね。企画課長の方から。
企画部企画課長 角田道夫
時期にしましては、今内閣官房からの口頭での回答をもって関係する団体にもう一度ご説明に歩いたり、さらなる要望等を聞くのと合わせまして試算の作業に入ろうとしているところですので、それらを踏まえますと連休明けのそれほど遠くない時点で考えさせていただきたいと思います。
12 「山の日」について
信濃毎日新聞 古志野拓史 氏
あともう一点すみません。山の日なんですけれども、先日設立された議連(超党派「山の日」制定議員連盟)の方で候補は6月の第一日曜がいいのではないかというような考えも今なりつつあるそうなんですけれども、県としては独自の山の日制定という動きもありますが、全国の流れとして6月第一日曜という線について、知事としてはどんなふうに受け止められるかお願いします。
長野県知事 阿部守一
それは私は直接まだ聞いてないからなんともコメントしようがないですね。これは長野県としても山の日を考えていかなければいけないと思っていますが、国の動きもにらみながら、県としての考え方、県の山の日の制定を考えていかなければいけないと思っています。その過程で広く県民の各界の皆さんからもご意見を聞きながら進めていかなければいけないと思いますので、そういう中で長野県としての日にちの設定等も含めて、幅広く考えていかなければいけないだろうと思っています。
信濃毎日新聞 古志野拓史 氏
すみません。補足で今年こういうタイミングでいろいろ山の話題なんかも出てるんですけど、これから観光シーズンが始まったりして上高地だと開山祭だとか、ウエストン祭だとか涸沢のいろいろなフェスティバルの関係だとか、アルプス中心にいろいろイベントがあると思うんですけれども、知事は今年そういう問題意識で行ってみようかなとかそんな感覚はありますでしょうか。
長野県知事 阿部守一
どこかの山に登りに行かなければならないかなとは思っていますが、ちゃんと携帯が通じるところとか、そういうことも勘案して決めていきたいなと思いますので、山の日の問題だけでなくて、山岳高原観光地づくりということも新しい「しあわせ信州創造プラン」の中に位置付けているところでありますので、そういう意味で少し山の方に私自身も足を向けるように日程調整等もしていきたいなと思っています。
13 道州制について
読売新聞 中村和裕 氏
道州制のお話に戻って恐縮なんですけれども、知事は慎重な立場を取られているということでしたけれども、なぜ慎重な立場を取られているのか、現時点での具体的なお考えを改めてお伺いできますでしょうか。道州制では例えばこれまでと違う広域的な行政サービスが可能になるですとか、そういったメリットを一方でもちろん指摘されていますし、知事が慎重な立場を取られている理由をお聞かせください。
長野県知事 阿部守一
そうですね、これは関西経済界の皆さんと話した時に言ったことでもあるんですけれども、まず今の関西圏とか首都圏が、例えば経済活動等を考えたときに、エリア的に適切かというところは恐らく議論があると思いますし、私もそう思います。これは実感として思いますが、横浜市役所で勤務していた時に、横浜、川崎、隣り合わせの政令市で、さらに多摩川越えればすぐ東京と。みんな通勤通学で行ったり来たりしているわけですよね。そういう関西圏であるとか首都圏で、じゃあ今の都道府県のエリアが本当に最適なのかということは、これはもう当然議論があるわけでありますし、橋下市長が問題提起した、とりわけ都道府県と政令指定都市の関係は長年これは二重行政があるんじゃないかとかですね、権限配分が中途半端じゃないかという議論は、どちらかというと大都市側、政令指定都市側から問題提起をされてきたテーマでありますから、そうしたことを考えれば首都圏なり大都市圏で今の都道府県、そして政令市をどういう区域にしていくのか、どういう機能を持たせていくのかということは当然検討されるべきものだと思いますし、私自身も横浜にいた時は当然そういう問題意識を持っています。ただじゃあ首都圏とか大阪で議論になっていること、あるいは首都圏とか大阪で問題になるようなことは、日本全国の問題かというと全然違うと私は思っていますね。長野県でそんな話を私は聞いたことがない。住民の間から、年中隣の県に通勤しているけど隣の県の福祉政策はこうだけど、うちの県はこうなっていておかしんじゃないかっていう話は全く聞いたことがない。そういう意味で大都市で暮らしている方、首都圏、関西圏で暮らしている方の感覚と私たち長野県の実情、感覚というのは全く違うと思っています。そういう意味では比較的大都市部からこうした問題が出てきていると私は思っていますけれども、そういうことを考えると、道州制が私は唯一最善の解ではないだろうということを関西経済界の皆さんにも申し上げました。都道府県合併でいいじゃないですかと、あるいは大都市制度改革でいいじゃないですかと、私は都道府県合併と大都市制度改革、そして国から地方への権限移譲、この3つができれば皆さんが道州制で実現したいと思っていることは実現できますよという話をさせていただいていますし、そう思っています。ですから、そういう意味で問題が今の地方自治制度に全くないと私も思っているわけではなくて、対応するべき課題はいっぱいあると思っています。それに対する解が道州制ということではないでしょうというのが私の感覚であります。あと他にもいろいろありますけど、横浜市、当時370万都市、もっと今人口増えていますけども、長野県よりでかいわけですよ人口が。そういうところで基礎自治体としての首長が一人だけということで本当に住民自治の観点から十分かという問題意識を私は常に感じていました。今度道州という例えば全国を10くらいの地域に分けて、そこに公選首長を置くというときに果たしてそれは自治体、あるいは地方自治という観点に立脚した組織に本当になり得るのかということも感覚的にはですね、結構疑問です。もろもろありますが、そういう意味で私は慎重な立場ということであります。
読売新聞 中村和裕 氏
ありがとうございます。
14 道州制に関する庁内WGの設置について(3)
中日新聞 小西数紀 氏
今の話の関連でワーキンググループの件なんですけれども、このワーキンググループで知事さん顧問になられるということで、知事さんの今までの道州制に対するご意見とこのワーキンググループでの議論の距離感っていうんですかね、知事さんの意見に沿ったような議論になるのか、それともまた、それはそれでひとつ置いておいて独自の議論されるのかというのをちょっとお伺いしたいんですけれども。
長野県知事 阿部守一
それは沿った議論ですよね。当然私が知事ですから、それは沿った議論になってもらわなきゃいけないですし、私がそういう形で関わるのは、これはとりわけ事務的な話であれば、課長以下ワーキンググループでやってもらうだけでいいのかもしれないですけれど、極めて政治的な部分があるわけですよね、政治的というのは変な意味での政治的な部分じゃなくて、要するに道州制になったときに首長っていうものの存在がいったいどうなるかみたいな話を課長とか係長が集まって議論するだけでは多分らちが明かないわけでありまして、そういう意味では私の感覚も入れていきながら、県としての考え方をまとめていくという形になろうかと思います。
長野県知事 阿部守一
はい。じゃあよろしくお願いします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください