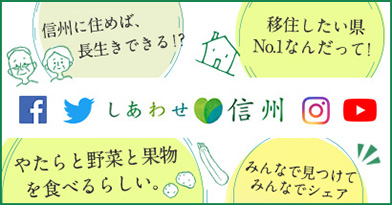ここから本文です。
更新日:2025年4月11日
長野県の緊急輸送道路
令和6年能登半島地震を踏まえ、より実効性の高い道路啓開計画による緊急輸送道路の早期確保のため、緊急輸送道路ネットワーク計画の抜本的な見直しを行いました。
今後の道路整備によって、より安全な緊急輸送道路ネットワークが形成された場合は随時見直しを行っていきます。
緊急輸送道路一覧表(長野県地域防災計画資料編より抜粋)(PDF:602KB)
地理情報システムでの閲覧はこちら
閲覧方法はこちら
緊急輸送道路とは
災害直後から応急活動のために緊急車両の通行を確保すべき重要な道路
緊急輸送道路の指定意義
- 幅員の狭い区間の拡幅・バイパス化、橋梁の耐震化及び落石等危険箇所の対策を重点的に実施
- 災害時に一部路線では国の権限代行による道路啓開が可能
- 新設電柱の占用禁止により電柱倒壊による道路寸断を防止
見直しの主なポイント
- 災害時に優先的に実施すべき活動の観点から防災拠点の選定基準を整理
- 基幹道路(高速道路や直轄国道など)から防災拠点の入口までを接続するルート(ラストワンマイル)を追加指定
- これまで指定していなかった市町村道も対象として追加指定
- 防災拠点まで複数のルートが指定されていた区間については災害に強い道路に一本化
防災拠点の設定
「長野県地域防災計画」に記載されている段階的な緊急輸送活動に基づき、防災拠点の定義は以下のとおりとする。
第1次防災拠点
- 県全体及び広域の災害本部機能を有する拠点
- 人命救助、消防等災害拡大防止、ライフラインの復旧(道路啓開活動)、交通規制を担う拠点
第2次防災拠点
- 各地域の災害本部機能を有する施設
- 食料・水・燃料等の輸送、被災者の救出・搬送、応急復旧活動、ライフライン(電気・ガス・水道・通信)の復旧を担う拠点
第3次防災拠点
- 生活必需物資の輸送を担う拠点
緊急輸送道路の設定
今回見直しした緊急輸送道路の指定基準は、以下のとおりです。
第1次緊急輸送道路
- 広域的かつ重要な路線で輸送の骨格をなす道路(高速道路、直轄国道等)【基幹道路】
- 基幹道路(第1次)同士を接続する道路【基幹道路】
- 基幹道路(第1次)と第1次拠点を接続する道路【拠点接続】
第2次緊急輸送道路
- 第1次緊急輸送道路の代替性を確保する道路【基幹道路】
- 基幹道路(第1次)と代替性確保路線を接続する道路【基幹道路】
- 隣県や広域相互を連携する道路【広域連携】
- 第1次緊急輸送道路と第2次拠点を接続する道路【拠点接続】
第3次緊急輸送道路
- 第1次、第2次緊急輸送道路と第3次拠点を接続する道路【拠点接続】
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください