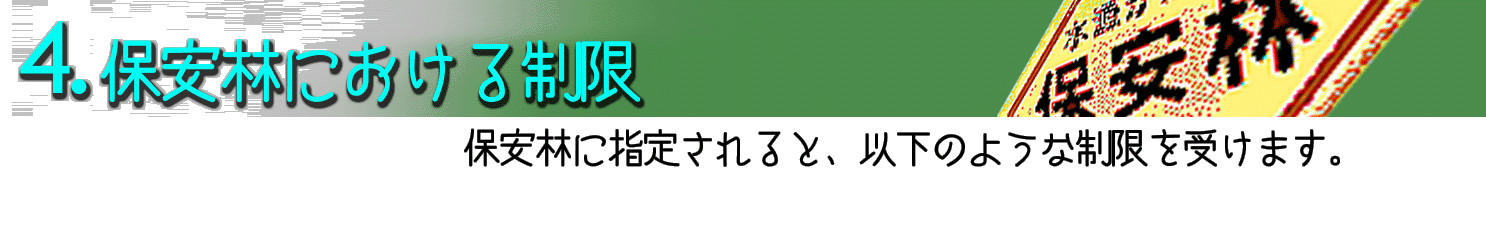ここから本文です。
更新日:2025年7月16日
保安林における制限
|
保安林に指定されたとき、立木の伐採の方法、立木の伐採の限度及び植栽についての内容を定めます。これを指定施業要件といいます。内容については以下のとおりです。
主伐とは、次の世代の立木を更新させるために行う伐採のことで、禁伐(基本的に伐採が許されないもの)、択伐(単木的な伐採が許されるもの)、伐採種を定めない(一定範囲の樹木を一時的に全部又は大部分伐採する皆伐が許されるもの)の3種類のいずれかを定めます。 主伐が可能な林齢を定めます。例えば長野県の場合スギ40年、ヒノキ45年、カラマツ40年などとなっています。 間伐の必要な箇所について間伐の有無を定めます。
水源かん養、防風、防霧及び魚つき保安林については20ha以下、それ以外の保安林については10ha以下の範囲内で皆伐できる適正な面積を定めます。 基本的に材積率で30%を上限として定めます。ただし、伐採後に植栽する場合には40%を上限とできます。 間伐のできる箇所については、材積率にして35%が間伐率の上限となります。
主伐後、植栽によらないと更新が困難な箇所について、植栽樹種・期間・方法を定め、植栽を義務付けます。
立木を伐採しようとする場合には、基本的に知事の許可が必要です。この際に適否審査が行われ、当該伐採が適正であると判断されれば許可されます。
以下に掲げるような行為をしようとする場合には、基本的に知事の許可が必要です。これらの行為が保安林機能の維持に支障がないと判断されれば許可されます。
これまでに挙げた制限に従わない場合、違反した場合などには、知事により以下のような監督処分が行われる場合があります。
|
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください