ここから本文です。
更新日:2025年11月13日
容器包装リサイクル法
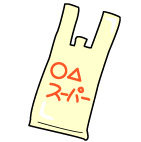
容器包装リサイクル法とは?
わが国の経済は「大量生産・大量消費」により、目ざましい発展を遂げてきましたが、その一方で、排出される廃棄物(いわゆる”ごみ”)は大幅に増大し、他方、最終処分場の許容年数はひっ迫している状況です。
また、一般廃棄物のうち容器包装廃棄物の割合が、容積比で約6割、重量比で約2~3割という大きな割合を占めており、これを削減及びリサイクルするための方法が求められていました。
これらを受け、平成7年6月に、容器包装リサイクル法が制定されました。この法律は、家庭から一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物の減量化及びリサイクルシステムを確立するため、消費者、市町村、事業者各々の役割分担を規定したものです。

容器包装リサイクル法のしくみ
容器包装リサイクル法では、消費者・市町村・事業者のそれぞれが責任を分担するしくみになっています。1.消費者は分別収集に協力し、2.市町村は容器包装廃棄物の分別収集を行い、3.事業者は、市町村が収集した容器包装廃棄物を、自らまたは指定法人やリサイクル事業者に委託して再商品化します。
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会(外部サイト)のホームページでわかりやすく解説されています。

第11期長野県分別収集促進計画
容器包装リサイクル法では、市町村が3年ごとに翌5年間の容器包装廃棄物の発生量及び分別収集量を予測し、また、発生抑制や分別収集促進に向けた施策をもとに、「市町村分別収集計画」を作成することになっています。また、これをもとにして、都道府県では「都道府県分別収集促進計画」を作成します。
長野県では、令和7年11月に、令和8年4月から令和13年3月までの5年間を対象期間とした「第11期長野県分別収集促進計画」を定めました。
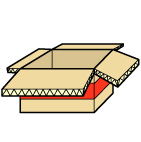
リンク
環境省(トップページ)(外部サイト)
経済産業省(トップページ)(外部サイト)
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会(外部サイト)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

