ここから本文です。
更新日:2017年4月1日
指導資料No.43 生命を大切にするために~自殺への理解と未然防止を~
毎年、数名の児童生徒が自らの生命を自らの手で断っています。本年度これまでに女子中学生、女子高校生の2名が尊い生命を断ってしまいました。遺族はもちろんのこと、級友や教師など周囲の人々に大きな衝撃を与えました。後に残った者たちの嘆き悲しみは言葉にならないほどです。
普段元気なときは自殺など自分とは無縁だと思っていますし、身近な人が自殺するなんて思いもよりません。ところが、人間は何か苦しいことに直面したり、ショックを受けますと、それがきっかけとなってうつ状態となり、「死んでしまいたい」と思ったりするようになるものです。様々な調査によれば、「死にたい」と思ったり、自殺を肯定的にとらえている中・高校生はかなりいます。このことは、彼らが、「死にたい」と思ったからといってすぐに自殺に結びつくわけではないにしても、いつどんな動機で自殺するかもしれない不安定な心理状態にあることを示しています。中・高校生でささいなことで自殺する恐れのある者が、クラスの中に一人か二人はいることを念頭におかなければならない、と指摘する専門家もいます。
自殺願望者は死を望みながらも生き続けたいと願っており、そのために様々なサインを出し続けます。自殺の予防はここに着目することによって可能になります。
自殺を防止するためには、家庭との密接な協力の下に、児童生徒に共感的な態度で接し、深い心の絆を結ぶことが大切です。本号を参考に自殺についての理解を深め、その防止に努めて欲しいと思います。
平成元年12月25日 長野県教育委員会 生徒指導幹
目次
1.児童・生徒の自殺の実態
自殺の状況
県下の公立小・中・高校の児童生徒の年度別自殺者数は表1のとおりです(教学指導課調べ)。
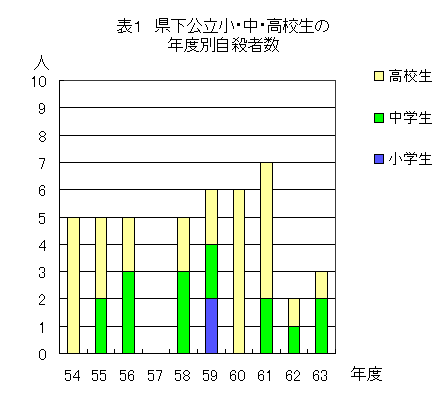
昭和54年度から昭和63年度までの過去10年間に、小学生2人(4.5%)、中学生15人(34.1%)、高校生27人(61.4%)計44人となっています。男女別では、男子31人(70.5%)、女子13人(29.5%)です。平成元年度は、11月末現在で中学生女子1人、高校生女子1人の自殺者が出ています。全国の公立小・中・高校の状況は表2のとおりです(文部科学省調べ)。
|
区分 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
|
総数 |
380 |
233 |
228 |
199 |
237 |
189 |
215 |
268 |
170 |
175 |
|
小学生 |
11 |
10 |
8 |
8 |
6 |
12 |
11 |
14 |
5 |
10 |
|
中学生 |
107 |
59 |
74 |
62 |
83 |
66 |
79 |
110 |
54 |
62 |
|
高校生 |
265 |
164 |
146 |
129 |
148 |
222 |
235 |
244 |
111 |
103 |
昭和54年度からの過去10年間の状況は小学生95人(4.2%)、中学生753人(32.8%)、高校生1,446人(63.0%)計2,294人となっています。
自殺又は自殺未ついにまでは至らないが、自殺念慮(自殺したいという思い)を抱く中・高生は40人の学級で8人~12人ぐらいいる、といわれています。
自殺の原因・動機
児童生徒の自殺の原因には、社会環境や家庭環境、あるいは児童生徒自身の性格、さらには学校における人間関係の在り方などが複雑に絡み合っていると考えられます。昭和63年度全国の公立小・中・高校生の自殺者175人の直接的原因・動機をみると表3のとおりです(文部科学省調べ)。
|
小学生 |
中学生 |
高校生 |
計 |
||
|
家 |
家庭不和 |
1(10.0) |
4( 6.5) |
7( 6.8) |
12( 6.9) |
|
父母等の叱責 |
1(10.0) |
6( 9.7) |
6( 5.8) |
13( 7.4) |
|
|
貧困 |
1( 0.6) |
1( 0.6) |
|||
|
その他 |
2(20.0) |
3( 4.8) |
3( 2.9) |
8( 4.6) |
|
|
小計 |
4(40.0) |
13(21.0) |
17(16.5) |
34(19.4) |
|
|
学 |
学業不振 |
2( 3.2) |
4( 3.9) |
6( 3.4) |
|
|
進路問題 |
3( 4.8) |
6( 5.8) |
9( 5.1) |
||
|
教師の叱責 |
|||||
|
友人との不和 |
3( 4.8) |
1( 1.0) |
4( 2.3) |
||
|
いじめ |
2( 3.2) |
2( 1.1) |
|||
|
その他 |
6(60.0) |
2( 3.2) |
4( 3.9) |
12( 6.9) |
|
|
小計 |
6(60.0) |
12(19.4) |
15(14.6) |
33(18.9) |
|
|
個 |
病気等による悲観 |
4( 6.5) |
6(5.8) |
10( 5.7) |
|
|
厭世 |
4( 6.5) |
10(9.7) |
14( 8.0) |
||
|
異性問題 |
6(5.8) |
6( 3.4) |
|||
|
精神障がい |
3( 4.8) |
16(15.5) |
19(10.9) |
||
|
小計 |
11(17.7) |
38(36.9) |
49(28.0) |
||
|
その他(原因不明等) |
26(41.9) |
33(32.0) |
59(33.7) |
||
|
計 |
10(100) |
62(100) |
103(100) |
175(100) |
|
(注)( )内は、理由別の構成比である。
その他(原因不明等)が59人(33.7%)と最も多く、次いで「父母等のしっ責」「家庭不和」等家庭事情によるものが34人(19.4%)「進路問題」「学業不振」等学校の問題が33人(18.9%)、「精神障がい」等個人的な問題が49人(28.0%)の順となっています。
自殺の特徴
- 衝動的
それまで特に変わったところがあるようには見えなかった子どもが急に自殺をしてしまうことが多くあります。年齢が低い程この傾向が強くみられます。冷静な判断ができなかったり、激情に駆られて前後の見境いがなくなりやすいことによるためと考えられます。 - 致死度の高い手段
首をつる、高層ビルなどから飛び降りる、列車に飛び込むなど大人は怖くてなかなかできないようなことをあえて実行するため、助かりにくく致死度は高くなります。 - 大人からみるとささいな動機
自殺の動機が大人から見ると何ともささいであったり、腑に落ちない感じのすることが多くあります。場合によってはなぜ自殺までするのかよく理解できないような事例もあります。特に年齢の低い子どもでは、そうした傾向があり、例えば親や教師に注意されたとか、欲しい物を買ってもらえない等の理由で自殺することもあります。このように、大人から見るとささいな動機のように見えるのですが、子ども自身にしてみるとそれぞれ死に値するような深刻な理由になっている点が重要です。 - 他の影響を非常に受けやすい
友人が自殺した後、自分も自殺をしてしまうとか、新聞などで子どもの自殺が報道されると同じような自殺が続発する、あるいは自殺した子どもの手記などを読んで自分もその後を追うといったふうです。昭和61年には、ある女姓タレントのビルからの飛び降り自殺の影響もあって、1年間に全国の小中高生268人が自殺しました。このように一人の子どもの自殺があった場合、その友人とか、級友、同じ学校の児童生徒などには特に注意する必要があります。心理的に未分化・未発達なため、判断力は乏しいし、自分の信念や考え方なども出来上っていないため、容易に動揺し、引きずられてしまうわけです。 - 生と死のけじめがはっきりしない
小学生ぐらいまでは、死ということがまだ観念的にしか把握されておらず、死んでもまた生き返ってくるとか、生まれ変れるものだなどと考えたりします。また死を苦しみを避けるとか、休養することぐらいに考えているようなこともあります。
特に女子では死にロマンチックな夢を描いたり、死後の世界を美化して、あこがれているようなことが少なくありません。そのために現実の苦しさや醜さから逃れ、死につこうという気持ちを強めてしまうことになるし、一時的にこの世から逃れる手段として自殺を考えがちです。 - その他
この他にも、登校拒否・家出・非行などから自殺に走ったり、友達に同情して道連れや後追い自殺をすることもあります。これらはいずれも子どもの心理の特徴に由来するものであり成人にはあまり見られません。
2.自殺の未然防止のために
自殺の心理
子どもの自殺には、さまざまな心理が含まれています。その主なものをあげてみます。
- 誰も分かってくれない
自分のことを誰も分かってくれず、見捨てられていると感ずる孤立無援感です。子どもの自殺では、大人に比べこの孤立無援感がとくに顕著です。 - 最後まで救いを求める
自殺をしようとする者は、生きたいという気持ちと死にたいという気持ちの両方が共存しており、深刻に悩んでいます。生きたいという気持ちが弱くなり、死を願うような状況になってしまっています。そうした中で、さまざまな形の救いを求めるサインを最後まで発し続けます。 - 相手を攻撃したい
どの自殺にも、大なり小なり攻撃性の要素が含まれています。大人以上に、子どもは攻撃性が強いといわれています。子どもは自分をいじめた者に対する復讐から自殺を選ぶこともあります。 - 自分を罰したい
自己に厳しく、気持ちの優しい内向的な子どもは、成績が悪かったとか、失敗して叱られたなどを契機に、必要以上に攻撃を自分に向け、悪い子であると決めつけて自殺という方法で罰します。 - 苦しさから逃れたい
現実の辛さや苦しさに耐えられず、苦しいこの世の現実から逃げ出そうとするものです。
子どもの置かれている家庭、学校、社会などの環境が大きく影響しています。 - 生まれ変りたい
「こんど生まれてくる時には……」と新たに生まれ変ろうとする願望です。子どもの場合には特にこの傾向が強いと見られています。 - 自分を認めてほしい
何とかして自分の存在を主張し、目立ち、認めてもらおうとする願いを、死によって果たそうとするわけです。同時に周囲を驚かせようとする気持ちも含まれています。
学校で配慮すべきこと
- 生命を尊重する教育
生命の尊さ、死の厳粛さなどを、児童生徒の発達段階に応じて、一層深く体得できるように、指導の充実を図らなければなりません。
例えば、児童生徒にとって身近な小動物を、学校や家庭で飼育する体験を通し、生命あるものの「生」をいとおしみ、「死」を考える教育を進める必要があります。 - 成就感、喜びをもたせる教育
ともすれば授業内容の理解が遅く、挫折感や劣等感を持ちやすい児童生徒には、きめ細かな適切な指導で学ぶ喜びをもたせ、将来に希望のもてる指導をすることが大切です。 - 児童生徒の実態の把握
「どうして、僕だけをいじめるのだろう。気の小さな僕には、もうこれ以上耐えられない。こんどは強い人間に生れかわってきます。お父さん、お母さん、ごめん。」と書き置きを残して自殺した中学1年生がいました。
誰にも相談できずに困ったり、悩んだりしている児童生徒がいないか、平素から注意深く観察する必要があります。子どもが何に悩み、何を生きがいにしているかを調査や検査、あるいは教育相談などによって把握し、その行動や感情の動きをできるだけ詳しく理解して指導に役立てなければなりません。- 学級の中の人間関係に、いじめなどの問題はないか。
- わがままな子がぶつかり合い、背を向け合っていないか。
- 厭世的になっている児童生徒はいないかなどについて特に注意を払う必要があります。
- 教師の資質の向上
体育の時間に「あなたは不器用ね」とみんなの前でいわれて、手首をナイフで傷つけた自殺未遂の女子生徒がいました。
教師自身はごく気軽にいったつもりの一言が原因で、その教師への不信が深まり、登校拒否に陥ったり、時には短絡的に死へと結びつくことがあります。- 年ごとに、さま変わりする児童生徒に対して、教師だけが昔のままの状態で子どもたちにかかわろうとしていないでしょうか。
- 児童生徒の「行為」を注意しているつもりで、その実、「人格」まで否定していないでしょうか。
- 生徒理解の充実
すべての教師が協力して、生徒指導体制の確立を図り、自殺のおそれのある生徒を早期に発見し、対応することが大切です。そのために教師は以下の内容について、個々の生徒を把握していかなくてはなりません。- 生育歴
・乳児期における栄養や病気
・乳児期及び幼児期のしつけ - 家庭環境
・本人に対する親の理解
・妊娠時、乳児期及び幼児期の親の状況
・親の性格とその特徴
・家族の構成と本人の立場 - 習癖
・神経症的習癖(顔面けいれん、まばたきなど)
・性についての特異な習癖 - 友だち関係
・交友関係の推移や現状
・問題グループとの関係 - 身体の健康状況
・病歴
・身体的な問題(アレルギー、ぜんそくなど) - 学校生活
・出席状況
・学業成績(成績の変化、教科の好き嫌い)
・学校生活への適応 - 検査・調査の結果
・知能、学力、性格検査 ?悩みの調査 - 直面している困難点
・身体的困難(太りすぎなど)
・家族関係
・学校生活(成績、友だち、クラブなど)
- 生育歴
- 家庭との密接な連携
「お父さん、お母さんと仲良くしてほしかった。もうお母さん帰ってこないかもしれない。どうして私一人残して行っちゃったの……」と母親に見捨てられた悲しさに耐えかね、自殺した女子高校生がいました。
特に、中・高校生の自殺には家庭内での問題に巻き込まれ、悩んだ未に自ら生命を断つ場合が少なくありません。
子どもが家庭生活に悩み、苦しんでいることを率直に話し合えるような信頼関係を父母と教師の間に作り上げ、密接に連携した指導に当たることが大切です。
家庭で配慮すべきこと
- 自殺のサインを見落とすな
子どもの自殺には、事前に必ず予告兆候、つまり自殺のサインがあります。「死にたい」「生きているのがいやになった」というような直接的な表現によるサインの場合もあれば、「学校をやめたい」というような間接的な表現によるサインの場合、また、身辺整理というような行動によるサインの場合などがあります。こうしたサインを受けた時には、その少年の気持ちを理解して支えることが必要です。決して無視したり、たかをくくったりしてはなりません。 - 子どもを孤独にするな
ふだん明るく、人を笑わせるような子どもであっても、親からみて何の不満もないはずという子どもであっても、淋しい孤独な心を抱いている場合があります。子どもを孤独に追いやる親は、概してうるさくつきまとってあれこれと口をはさみ、子どものいうことを簡単に拒否する自己中心の親に多いといわれます。 - 死の教育をするな
「お前みたいな人間は死んでしまえ」などという言葉を不用意に口にするのは、死に追いやる教育をしているようなものです。「死」や「生」の意味を正しくとらえさせる教育を、慎重な配慮の下に行われなければなりません。 - 子どもの頭で考えよう
子どもと大人とでは、知識や経験の量も、判断の内容も違います。大人の考え方だけで子どもを見、物事を要求したり、叱ったりすることは、子どもの心をゆがませることになります。子どもの身になり、まず子どもの立場で考えてその後、大人の考え方を加えて語るべきです。 - 家庭ではよく話し合おう
中・高校生になった子どもは、表面では親に反抗したり、しゃべらなくなったりしていても、心の中ではよい話し相手、相談相手としての親を求めています。普段から、親子が理解し合えるような内容のある対話を交していることが必要です。 - 親は聞き役に回れ
親子の対話で大切なことの一つは、親が子どもの話を最後までよく聞くことです。子どもの話を聞いてくれない親、自分ばかりしゃべっている親、初めは聞くが途中で怒ってしまう親、子どもの話をすぐけなす親などは子どもの気持ちや本当に言いたいことの内容をとらえることができません。 - 夫婦は仲よくしよう
両親の不仲の影響を受けて、その犠牲になったと思われる事例がたくさんあります。このような悲劇を生じないために、夫婦の仲がよく、いつも明るい家庭であることが必要です。 - 子どもは模倣で育つ
子どもは、日常の言葉や動作のみならず、その感情をも、親や周囲の大人から模倣しています。生命を大切にする習慣や感情も、親や教師や社会から模倣し、学んでいくものです。生命尊重のための情操を養い、しつけを行うことや環境を整えることは、大人の重要な仕事です。 - しつけは普段から
自殺する子どもには、さまざまな性格があります。中でも、すぐ人に頼ったり逃避したりしやすい性格、あるいは潔癖性で物の見方、考え方に柔軟性がなく、自分の考え方にこだわりやすい性格の子どもなどが自殺に向かいやすいといえます。これらの性格をも含めて、それぞれの性格に合ったしつけを普段から行い、生き抜くことの重要さを、次第に体得できるよう図らなければなりません。 - 親自身の性格を見直そう
一般に、自殺しやすい性格は、逃避しやすい人、挫折しやすい人、神経質で几帳面、きまじめで融通性のない人、依存的で、未熟な人、情緒の不安定な人、必要以上に劣等感をもちやすい人などと言われています。自殺した子どもの親をみると、子どもと同じ性格をもっている場合が多いといわれます。子どもの性格を直そうとする前に、親自身がまず自分の性格を見直し、改める必要があります。
自殺への経過
自殺は決して突然起きるわけではありません。一般的には、まず自殺を思い始める時期があり、その思いが次第に高まり、自殺を思いつめる時期へと移ります。この時期に何らかの動機があって自殺に至るといわれています。
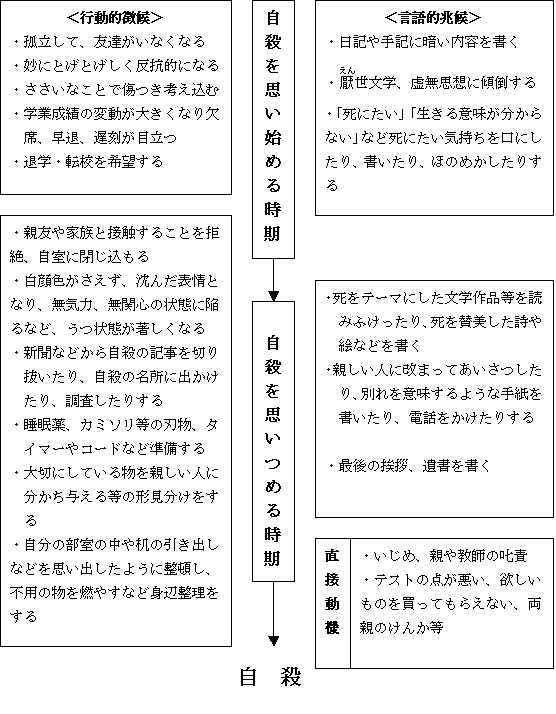
自殺未然防止のためのチェックポイント
- 学習について
- 学習意欲が突然なくなり、成績の低下が著しい。
- 急に欠席、早退、遅刻が増える。
- 友達や教師との関係について
- 一人でいることが多くなる。
- 特定の友達の悪口をよく言う。
- 特定の教師に対する強い不信感を持つ。
- 用もないのに職員室、保健室や教師のところへ来ることが多い。
- 神経症的習癖について
- 爪をかんだり指をしゃぶる。
- 不眠を訴える。
- 食欲をなくす。
- 言語や行動などについて
- 顔色も悪く無口になる。
- 突然大声で騒いだり、泣いたりする。
- 何かにおびえている。
- 人を避けようとする。
- 物ごとを必要以上に気にしたり心配する。
- ぼんやりしている事が多くなる。
- 落ち着きがなくなる。
- 独り言をよく言う。
自殺が発生した場合の対応
未遂であれ、既遂であれ、自殺問題が発生することは大変不幸なことであり、あってはならないことです。子どもの自殺こそなんとしても防がなければならないことは言うまでもありません。不幸にして事故が起きた場合、学校としてどのように対応したらよいでしょうか。
考えもしなかったこと。
なぜわが子が。
なんて馬鹿なことを。
どうして話してくれなかったの。
自殺者が出た場合、最も衝撃を受けるのは、言うまでもなくその遺族、特に両親です。その心情ははかり知ることのできないほどで、時には錯乱状態に陥ることさえあります。寝込んでしまう者、急に老け込む者、立ち直れなくなる者など、危機状態に追い込まれてしまうこともみられます。このような遺族の大きな悲しみをしっかりと基本にふまえて、学校関係者として、子どもの自殺については適切な対応をしてゆかねばなりません。
遺族への対応
- 誠意をもった対応
多くの場合はつらい、やりきれない気持ちにさせられるもので、ほとんどの両親は錯乱状態に陥り、時には攻撃的と思えるような問いをなげかけてくるかもしれません。そんな時、戸惑うことなく、自分の気持ちに耐えながら、親の気持ちになって、誠心誠意尽くすことが大切です。 - 遺族の気持ちの理解を
残酷な現場に直面した時など、とり乱している姿に接することが多くあります。これも当然のことで、もがき苦しんでいる心の奥を読みとり、その言動に左右されることなく、表面的にその場をつくろうような対応にならないよう、親の悲しさ、つらさに対応していかねばなりません。そしてその心情を実感として分かろうとすることが基本的な姿勢です。時として厳しい場面に遭遇します。その時、気後れしたり、また強引な態度、非難めいた言動などは慎まなければなりません。事故直後より時が経つに従って、悲しみがより深くなってくるものです。こんな時こそ、周囲の助けが必要になってきます。その場限りでなく、真の理解の下での継続的なかかわりを持つことが求められます。
学校の対応(学校管理下における場合)
思いがけないできごとに学校では、生徒はもちろんのこと教師集団、PTAにもその衝撃は大きく、動揺は隠せないものです。どんな場合でも、冷静沈着で、的確な対応に迫られます。
緊急処置
自殺が発生し、最初通報を受けた教師はまず校長に連絡します。連絡を受けた校長はいち早く現場へ急行、現場指揮に当たると同時に、教頭を学校に待機させ、緊急の学校体制を組織させ、指示を与えます。
教務主任、各学年主任、生徒指導主事を集め教頭と共に緊急対策を練ります。
養護教諭は学校医と連絡をとり当面の処置について指導を仰ぎます。
校長(または教頭)が所管教育委員会へこれまでの経過と学校のとった処置について簡潔に速報を入れ、必要な助言、指導を仰ぎます。
PTA会長に連絡をとり必要が生じた場合は遺族の対応にあたってもらいます。
表4 学校管理下における場合の緊急処置とその流れ
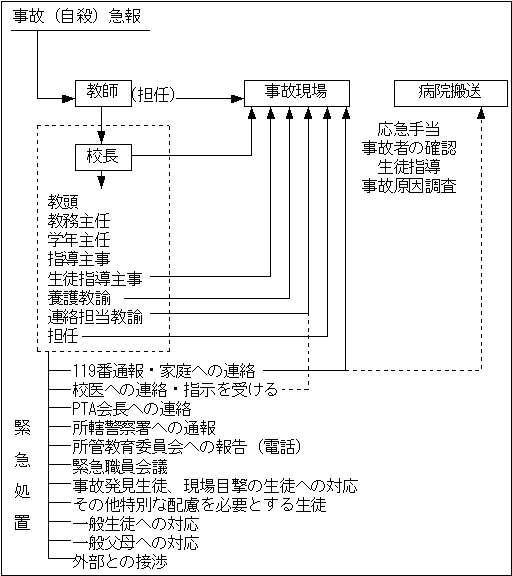
2.緊急職員会を召集
応急処置にめどがついたら、校長は学校に戻り、本部での打ち合わせに基づいて緊急職員会に臨みます。この職員会では正確な情報のもとに、教師の共通理解を図らねばなりません。そして事故発生以来の経過を逐一克明な記録にとどめておきます。
- 事故経過の報告確認
- 緊急処置およびその対応の報告
- 事故原因の説明
- 本人、家族、現場の状況説明
- 学校としての基本方針
- 一般生徒への対応
- 事故発見生徒、目撃した生徒、本人と仲の良かった生徒、原因となった生徒への指導
- 警察の事情聴取、現場調査への対応
- 生徒への指導、保護者対策
- 今後の予想される問題点
- 外部との接渉
以上が学校の対応の基本ですが、実際の場面では、更に複雑な事態も予想されます。例えば事故生徒の家庭が留守、交通通信事情の混乱、校長が出張で不在等が考えられます。平素、緊急事態を考慮して学校体制を確立しておくことと、職員の役割分担を確認しておくことが不可欠です。
3.外部との対応
外部に対しては責任者を決めて対応します。
教師の基本姿勢
自殺者とその家族に対する心からの哀悼を示しながら、事にあたることが最も大切なことです。
- 冷静な事態の認識
自殺ではその意外性や突発性のため、極度の不安定な状態に陥りやすく茫然自失、狼狼するようなことがあります。落着いた態度で事態を把握して冷静に対処しなければなりません。
教師の混乱は生徒に重大な影響を与えます。 - 正確かつ確実な情報の伝達
誤った情報、早合点や勝手な解釈、憶測は厳に慎まなければなりません。 - 迅速かつ的確な対応
可能なかぎり素早く、状況に即した臨機応変な行動が必要です。 - 指示、実行及び報告の励行
校長を中心とした全職員のチームワークが大切です。
生徒に対する指導
事故発生後、必要があれば全校集会を開き、校長は不安と混乱を静め、冷静かつ厳粛な態度で、事実をわかりやすく簡潔に伝えます。この場合、詳細にわたったり、自殺ということを明言する必要はありません。生命の尊厳を強調し、いかに苦しいことがあっても前向きに生きるべきことを言葉だけでなく、心情として、表情や態度をとおして伝えなければなりません。なお、状況に応じて学級単位など小集団を対象に補足することも大切です。
緊急処置後の対応
- 葬儀への生徒の参加は、第一に遺族の意向を尊重し、誠意をもって弔意を表すよう指導する必要があります。
- 学級では事故発生後の生徒の動向に注目し、意識、話題を可能な限り注意深く掌握しておかなければなりません。
- その後の遺族に対しては時をみはからって弔問に伺います。慎しみ深い態度でていねいな弔意を表します。遺族が一日も早く立ち直れるような配慮をすることが大切です。
4.指導実践事例
自殺(未遂)を図ったA子(高3)の指導
1 問題行動の概要
A子は6月のある朝早く、増水した川の堤防を睡眠薬を飲んで、ふらふらしながら歩いているところを、通りかかった車の運転手に保護された。そこで入水を図ろうとしたらしい。直ちに119番へ通報し、救急車で病院へ運ばれ手当てを受けた。
幸い、睡眠薬の量が少なかったために生命には異常がなかった。
知らせを聞いて両親も病院へ駆けつけた。母親は、朝食を知らせに彼女の部屋へ行って本人がいないのに気付き、心配し、周りを探していた。
A子は、約半年ほど前に「最近どうも気分が優れない、勉強も能率が上がらず、学校が嫌になった」と担任に訴えたことがあった。その後も、気分はあまりすっきりしない日が多く、憂鬱そうに学校生活を送っていた。
2 A子のプロフィール
- 家族環境
両親、兄、本人の4人家族。近くには祖父母(父方)が住んでいる。父は非常に仕事熱心。企業戦士で、帰宅時間の遅い日が多い。母親も、ある会社で仕事をしており、共働きである。兄は、大学2年に在学している。
兄妹は、小さい時から祖父母に育てられた期間が長く、保育園にも早くから入り、本人たちにしてみれば、母親の愛情を肌で感じた機会が少なかったように思われる。
父親は、子どもたちの学業成績等が気にはなっているが、子どもの教育、躾等については母親任せである。時々話をすることはあっても「しっかり勉強しろ」と、勉強のことくらいである。しかし、父の兄弟がいわゆる一流校出身ということで、自分の子どもたちには大きな期待感を持っている。 - 本人の状況
本人の現在の学業成績は、全般的には上位にあり、本人の努力次第では、国立大学進学も可能な位置にある。
しかし、3年になって最初の進学模擬テストではあまり振るわず、国語を除き、他はあまり良い成績ではなく、落ち込んできている。性格的には、明るい方ではないが、小さい時から運動は嫌いではなく、一時的ではあるが体操教室へ通っていたこともある。
現在は、バスケットクラブに所属しているが、あまり活動はしていない。
3 問題行動の原因・背景
A子が自殺を図った原因には、次のようなことが考えられる。
- 両親の、彼女に対する期待過剰が重荷となり、不安になってきている。
- 幼児の頃の、親に対する愛情の欲求不満と、期待過剰とが重なって不満が一層募ってきたものと思われる。そのために、気分が不安定となり、いらいらし、勉強にも打ち込めなくなってきている。その結果が、模擬試験の成績に現れてきている。
- クラブも欠席がちで、技術の向上にも伸びが見られず、友人ともだんだん疎遠になった。彼女に対して無関心の生徒が多くなり、現在、ほとんど話し合える友人がいない。
家庭、学校生活での悩み等を打ち明けたり、いろいろ話し合い、相談にのってくれる人が得られず、気が滅入っていたのではないかと思われる。
4 指導の対策
A子の問題行動発生後、学年会、生徒指導係会、職員会議等を開き、原因・背景等について研究会をもち、A子を含め、生徒の自殺防止対策について協議し、対応して行くことにした。
- 学級の生徒への配慮
今回のA子の欠席については病気ということで生徒には対応し、もし知られるようなことがあっても、必要以上に隠しだてせず、学級の生徒が動揺することのないように配慮する。
また、HR、教科指導のなかで、人間としての生き方、在り方、生命の尊重等についても触れ、生徒自身が積極的に考え、希望をもって生活出来るような指導をするとともに、生徒同士が、お互いに信頼し、相談し合えるような雰囲気づくりにつとめ、温かい人間関係が育まれるよう援助していく。 - 親への対応
事故の翌日、学級担任は生徒指導主事と家庭訪問し、次のような点に努力してもらうよう要望した。- 親子の関係を反省し、その改善を図ること(親子の心の枠を結び直し強固なものとする)
- 両親がA子と接する時間をできるだけ多く取り、愛情のこもった関わりをすること。
- A子が抱えている悩みに親も本人の立場に立って一緒に考え、理解するよう努めること。
- 学校の反省・見直し
A子に対してはもちろん、もっと生徒理解に意を注ぎ、深めて行くことが大切であると次のような点を確認し合った。- 本人の日常の行動、学習活動、クラブ活動等学校生活の状況について、把握、理解を深める。
- 学年会、教科担任、生徒指導係、養護教諭、クラブ顧問等々が密接な協力体制をつくり、自殺企図に結びつくような兆侯を事前に察知するよう努める。
- 学級担任を窓口とし、家庭との密接な連携をとり、誠意をもって親と接し、家庭の状況、親の気持ちを理解するよう努める。
- 学級、クラブにおける友人関係の改善が図れるよう援助する。
- 必要によっては、精神科医の診断が受けられるよう援助する。
5 指導の経過
事故の数日後からA子は登校するようになった。しかし、まだ不安定になった気持ちは完全には回復せず、全ての授業には出席出来なかった。保健室へ行っては養護教論と接触することが多かった。担任は養護教諭と連絡を取り、気分の回復するのを待った。約1ヶ月程で担任あるいは、相談係との会話も多くなってきた。
担任、相談係、教科担任、クラブ顧問等が連絡を取り、本人の状況を観察しつつ、次のような指導をした。
- 読書の領域が偏らないように注意する。とかく自殺念慮の生徒は、厭世文学作品を読みふけったり、センチメンタルな作品を好んだりする傾向があると言われることから、偏らない読書指導をした。
- バスケットクラブの練習にも参加を促し、体を動かし、気分の回復と体力の回復を図るなど、多様な活動を取り入れて行くように指導した。
- 相談係は、面接の中で雑談をしたり、悩みを聴きながら、生きがいや人生の意義について語り合い彼女の心に触れる内面指導をした。
2ヶ月程で、完全ではないが、以前の状態に近い表情に戻ってきた。
一方家庭では、母親が勤務の時間を短くし、本人と一緒にいる時間を多く取るように心がけた。
心の余裕ができてきてから担任との会話の中で、あのような行為をしてしまった心境をチラッと話したことがあった。『小さい頃は本当に寂しかった。いま考えれば、忙しい親に迷惑をかけまいと、いい子ぶって我慢していたのかも知れない』と。また『死んでしまいたくて堤防に行き、睡眠薬を飲み、川に転落したかった。しかし、死ぬことが怖かったこともあって、致死量を飲めなかったのかも』と。
明るさが戻りつつあっても、条件が悪化すれば、いつまた同様な行為を引き起こさないとも限らない。引き続き注意をしてゆく必要を感じている。現在、心配なのは、学級の生徒、クラブの生徒に働きかけているのだが、まだ親しい友人が出来ないことである。
この資料のために引用した文献
- 生徒の問題行動に関する基礎資料―中学校・高等学校編―昭和54年 文部省
- 子どもの自殺防止のための手引書 昭和56年 総理府青少年対策本部
参考文献
- 自殺のサインをみのがすな 稲村博 農山漁村文化協会
- 子どもの自殺 稲村博 東京大学出版会
- ぼくは死にたくなかった 大原健士郎 日新報道社
- 子どもの自殺 大原健士郎 朱鷺書房
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください